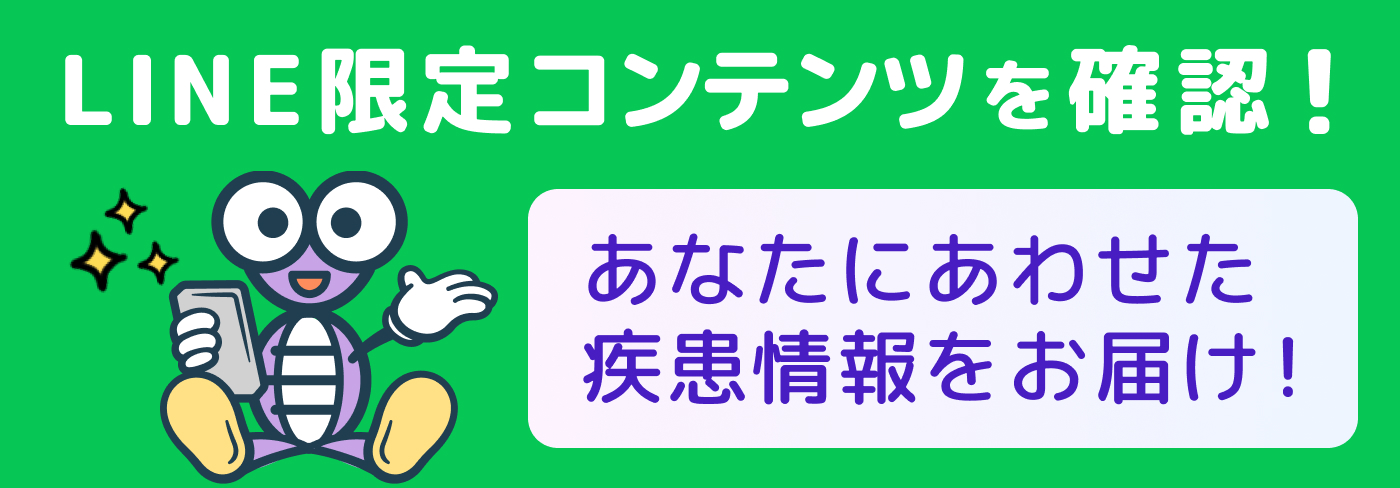国内患者数約500人、発症との関連不明な遺伝子変異を伴うことも
京都大学は、家族性地中海熱について、新たな診断方法を開発しました。
家族性地中海熱は、激しい腹痛・胸痛を伴う発熱発作を周期的に繰り返す疾患。名前が示す通り地中海沿岸に患者さんが多く、日本国内の患者数は500人程度とされています。炎症に関係するタンパク質「パイリン」の異常が原因とされていますが、病気との関連性が不明な遺伝子変異が見つかることがあり、その変異が発熱の原因になっているかを判断するのが困難でした。
治療薬として「コルヒチン」が有効とされていますが、同剤が無効または副作用で使えない場合には、発熱物質であるインターロイキン1βに対する抗体製剤が有効です。
遺伝子変異のある患者さんで分泌が多い物質を特定、新検査法を開発
今回、家族性地中海熱の患者さんから血液の提供を受け、詳細に検討。結果、典型的な家族性地中海熱の遺伝子変異がある患者さん由来のマクロファージ(体内の細菌や異物などを食べて消化する免疫細胞)は、遺伝子変異のないマクロファージと比べて、発熱物質インターロイキン1βを多く分泌することを発見しました。また、その分泌はコルヒチンの投与により抑制されることも確認されました。
研究グループはこれまでiPS細胞を用いた免疫疾患の研究を行ってきたことから、この発見を基盤として、iPS細胞技術を用いた検査方法を新たに開発。インターロイキン1βをたくさん分泌するかどうかを検査することによって、種々の遺伝子変異が家族性地中海熱の原因かどうかを判定する方法を見出しました。
「小児科を含めた医療現場では、家族性地中海熱の遺伝子検査結果の解釈に混乱がありました。今回の研究成果はその解決につながる結果です。この細胞を使うことで、効果や副作用の点でより優れた治療薬候補の探索も進めていきたい」と、研究グループは述べています。(遺伝性疾患プラス編集部)