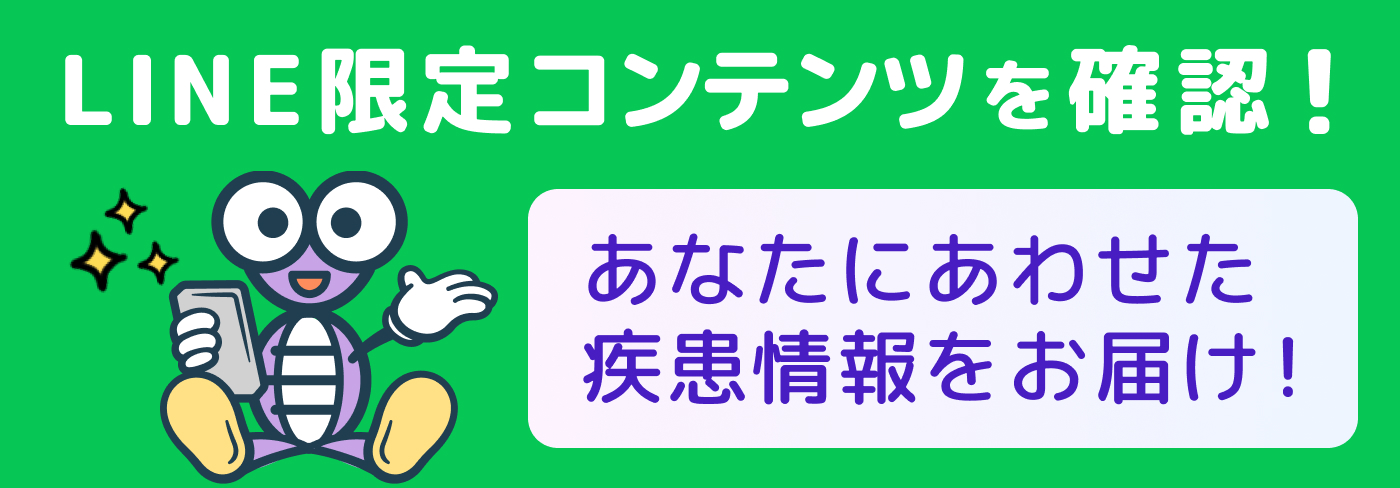ゾニサミドは効果の持続時間が長いが、個人差がある
神戸大学を中心とした研究グループは、パーキンソン病に用いられる「ゾニサミド」を服薬する患者さんを対象に遺伝子解析調査を行い、遺伝子型の違いにより、薬の効果が持続しやすい人と、そうでない人がいることを明らかにしました。
パーキンソン病において、「レボドパ」と呼ばれる治療薬が用いられることがありますが、同剤を用いた治療は、効果が短時間で切れてしまい動けなくなってしまう、いわゆる「ウェアリングオフ現象」が課題となっています。効果が切れることを恐れて過剰服用すると、不随意運動(体が勝手に動く)が引き起されます。一方、「ゾニサミド」は、効果の持続時間が長いためウェアリングオフ現象を軽減することができますが、個人によって効果が異なることがわかっています。
そこで研究グループは、どうして差が生じているかを明らかにするために、パーキンソン病でゾニサミドを服薬している患者さん200人について、遺伝子配列の違う場所を調べる「ゲノムワイド解析(GWAS)」を実施しました。
MDM4遺伝子の1文字の違いが効き目に影響を及ぼしていると判明
その結果、服薬前と比べて、症状が現れない時間が1時間半以上増えたグループの患者さんは、「MDM4」という遺伝子に、SNP「rs16854023」があることがわかりました。この有無がゾニサミドの効果に影響していることも明らかになりました。
SNPは、スニップと呼ばれ、DNAを構成する多数の「塩基」のうち、1つの塩基が別の塩基に置き換わったものをいいます。この遺伝子型の患者さんは、そうでない患者さんと比較して、症状が現れないオフ時間の平均が7倍以上延長されていました(1.42時間 vs 0.19時間)。この結果は、あらかじめ遺伝子型を調べておくことで、ゾニサミドの持続時間を把握し、投薬の管理を改善していくための基礎となる発見だといえます。(遺伝性疾患プラス編集部)