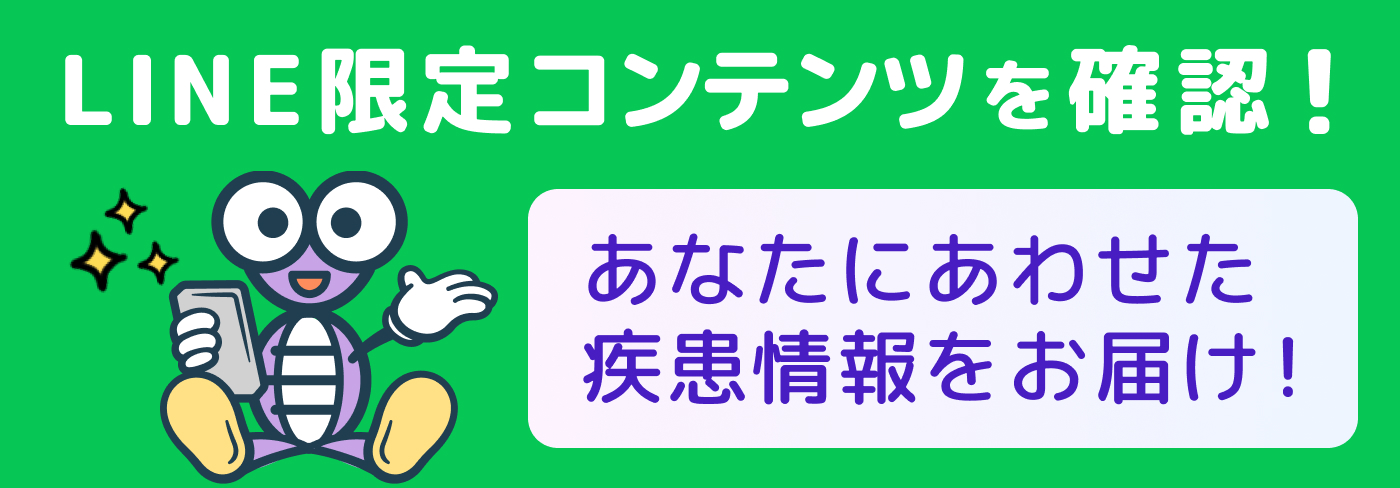自閉スペクトラム症との関連が注目されるFOXG1遺伝子
東京女子医科大学の研究グループは、社会的な活動に困難を伴う「自閉スペクトラム症」の発症に関連すると報告されている「FOXG1」遺伝子に着目し、この遺伝子に異常を持つモデルマウスの樹立に成功。作ったモデルマウスを活用することで遺伝子の異常な発現が生後2週間の離乳前に起こった場合に病気につながりやすいことを突き止めました。
子どもにおいて自閉スペクトラム症は約100人に1人の頻度で起こるとされていますが、発症メカニズムはまだよくわかっていません。発達期のどの段階に注意すればよいか、あるいは脳や神経のどのような働きに注意すればよいのかがわかれば、早期診断や早期治療などにつながる可能性があります。
そうした中で、自閉スペクトラム症との関連が注目されているのがFOXG1という遺伝子です。「iPS細胞(人工多能性幹細胞)」を使った研究などを通して、この遺伝子に異常があると神経活動が過剰になりすぎないようにする「制御機能」がうまく働かないことがわかっていました。ほかの研究でも、FOXG1遺伝子が重複して存在することでこの遺伝子から作られるタンパク質の量が増える場合(遺伝子重複)や、逆にFOXG1遺伝子変異によって作られるタンパク質の量が減少した場合(ハプロ不全)に自閉スペクトラム症の発症につながりやすいとわかっていました。
生後2週間の離乳前に異常が現れると発症につながる
今回、研究グループは、FOXG1に関連する遺伝子を人工的に操作したモデルマウスを作ることに成功しました。その上で、このモデルマウスの研究から、確かにFOXG1が増えた場合および減少した場合の双方において、自閉症に特徴的な社会性行動の異常が起きたり、患者さんと同様な脳波異常が起きたりすることを確認しました。
また、発達期の段階とFOXG1の増減との関連を調べることで、生後2週間の離乳前に自閉スペクトラム症の発症を左右する「臨界期」があることを確認。この時期に神経活動が過剰にならないようにコントロールしている脳回路の「抑制系」がうまく働かない減弱を見せると自閉スペクトラム症の発症に至りやすいことも突き止めました。
また、脳回路の抑制系をさらに弱めることで症状が悪化するほか、逆に弱まった抑制系を強めることで症状が回復することも確認。抑制系の強化が治療効果につながる可能性についても確認しました。
モデルマウスの利用によって、神経活動の異常と自閉スペクトラム症の発症との関係をより明確にすることで、自閉スペクトラム症の早期診断、早期治療、適切な療養につながってくる可能性があります。(遺伝性疾患プラス編集部 協力:ステラ・メディックス)