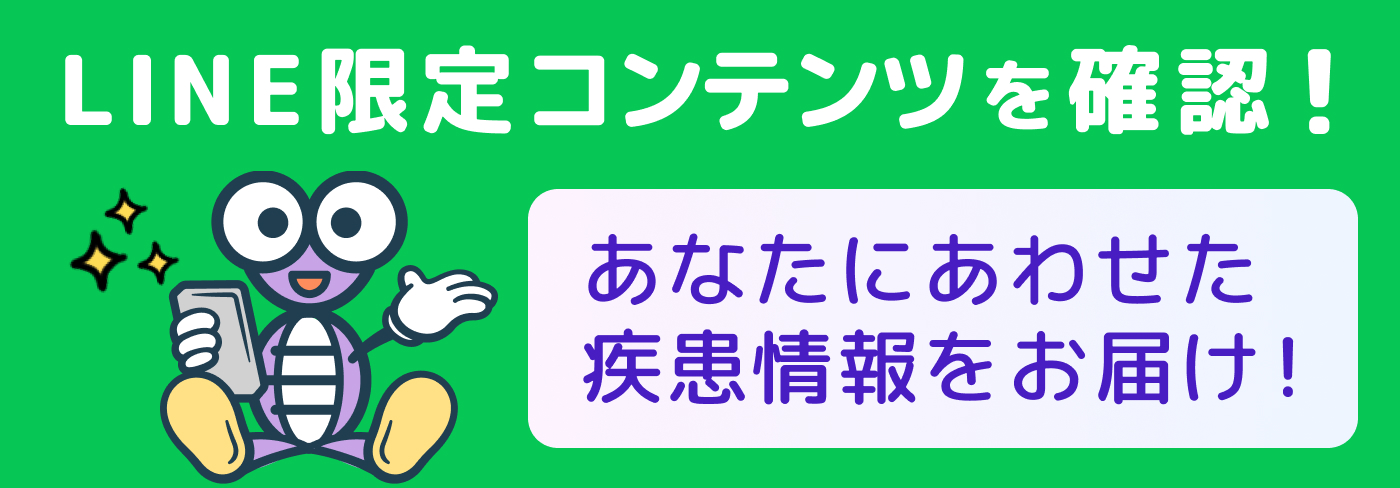「うちは”がん家系”なのよ…」というような話を時々耳にしますが、がん家系とは一体どのような家系のことを言うのでしょうか。また、海外の女優が、遺伝性のがんの予防で乳房を切除したというニュースも記憶に新しいと思いますが、彼女は切らなければ、必ず乳がんになったのでしょうか?
ここでは、遺伝性のがんを専門に診療しておられる、千葉県がんセンター遺伝子診断部部長の横井左奈先生に、子どもへの遺伝や発症の仕組みから、遺伝子検査の現状、普段から行える予防など、さまざまな疑問について、お答えいただきました。

「がんは遺伝子の病気」と言われますが、がんも遺伝性疾患と考えて良いのでしょうか?
遺伝性疾患という言葉は、”医学的”には、1つの遺伝子だけが変化して起こる「単一遺伝子疾患」から、多くの遺伝的な要因と環境要因が複雑に絡み合って起こる「多因子疾患」まで、遺伝が関与する幅広い病気を指す言葉として使われています。多くのがんは多因子疾患に含まれますので、その意味ではがんも遺伝性疾患と言えます。ただ、一般的に“診療の現場”で遺伝性疾患として扱われているのは、単一遺伝子疾患です。その理由は、多因子疾患は、まだ全貌が解明されておらず、診断することも、それを基に診療を組み立てることも難しいからです。医学的には理解されていても、診療するにはまだよくわからない部分が多いため、診療の現場では、今のところ多因子疾患を含めずに考えているわけです。
一方で、ほぼ全てのがんは、何らかの遺伝子変化によって起きています。ややこしいのですが、「遺伝子変化」と「遺伝的変化」は、ちょっとニュアンスが違います。「遺伝子の変化がある」ことと、「遺伝する」ことは、別なのです。遺伝的というと、通常は、子どもに受け継がれる細胞(生殖細胞系列)に遺伝子変化を持つ状態を指します。生殖細胞系列に、がんに関連する遺伝子変化(がん関連遺伝子の変異)を持っているがん患者さんは、成人がん患者さんの5~10%です。
この人たちも、生まれつき持った1つのがん関連遺伝子が原因で、全員が最初からがんを発症しているのではなく、ほとんどの場合、成長していく過程で体の細胞に遺伝子の変異が加わって、がんを発症するのです。一方、生殖細胞系列にがん関連遺伝子の変異を持たない人も、がんになるわけですが、そのような人たちは、成長の過程で体の細胞にいくつもの遺伝子変化を蓄積していき、やがてがんを発症します。結局、がん関連遺伝子に変異を持つ持たないにかかわらず、がんになるときには遺伝子変化が起きるというわけです。
生まれつきがん関連遺伝子に変異を持つのと持たないのとでは、がんの”なりやすさは”どのように違うのでしょうか?
実は人間は、多くのがん関連遺伝子を持っているのです。その中で、遺伝性のがん(遺伝性腫瘍)の原因となるがん関連遺伝子は、「がんのなりやすさにかなり強力な影響を及ぼす遺伝子」だと言えます。こうした遺伝子の1つに生まれつき変異があった場合、人生のどこかであと1つ、別のがん関連遺伝子に変異が入ると、がんになります。一方で、多くの人は遺伝性腫瘍の原因となる変異を持たずに生まれてきます。そして、生きていく過程で、いろいろな遺伝子変異が降り積もっていきます。やがて、がん関連遺伝子に、例えば4つとか、いくつかのセットで変異が入ると、がんになります。そのため、生まれつきがん関連遺伝子に変異を持っている人の方が、そうでない人に比べて、がんが早く発症しやすいと言えます。
「がん家系」とは、どのような家系を言うのでしょうか?
一般の人たちは、自分の家族(夫、自分や夫の両親、きょうだい、祖父母など)に、がんの人が何人もいるような場合に、「うちはがん家系だ」と思うのではないでしょうか。しかし、遺伝学的には「自分の家系」と「夫の家系」は全く別物です。
「医学的ながん家系」とは、血縁者の中にどれくらいがんの人がいるか、どんな種類のがんが発症したか、発症年齢は何歳くらいか、などによって考えます。例えば、おばあちゃんも乳がん、お母さんも乳がん、私も乳がん、お姉さんも乳がん、といったように、同じ種類のがんが血縁者に発症している場合や、自分は28歳で大腸がん、お父さんは35歳で大腸がん、おじさんは30歳で大腸がん、など、一般にがんになりやすい60~70歳代前後ではなく、若年で発症している場合、さらには、右の乳がんができて、何年後かに左も、転移ではなく原発として乳がんができた、などという場合に、医学的ながん家系を考えます。
親から子へ“必ず”遺伝するがんはあるのでしょうか?
遺伝性腫瘍の原因となる遺伝子変異は、ほとんどが「常染色体優性遺伝」という遺伝形式で、親から子へ伝わります。この形式に従う場合、両親のどちらかがその変異を持っていると、子どもに遺伝する確率は50%です。しかし、実際に生まれてきた子どもは「遺伝した(変異を受け継いだ)」または「遺伝しなかった(変異を受け継がなかった)」のどちらかであるため、自分の子どもに100%の確率で遺伝したかのように見えることもあります。例えば、子どもが2人いた場合、「2人とも遺伝した」「1人は遺伝したが1人は遺伝しなかった」「2人とも遺伝しなかった」のいずれかになりますが、偶然「2人とも遺伝した」であった場合、見かけ上100%遺伝したかのようになります。
さらに、遺伝性腫瘍の原因となる遺伝子変異を受け継いだからといって、100%がんを発症するかというと、決してそうではありません。遺伝性腫瘍は、まず親から遺伝性腫瘍の原因となる遺伝子変異を受け継ぎ、生きていく過程で他のがん関連遺伝子に変異が入って発症するからです。変異を受け継いだ場合に実際に発症する確率を「浸透率」と言いますが、遺伝性腫瘍の多くは、浸透率が100%ではありません。こういうところが、遺伝性腫瘍の理解しにくいところだと言えるかもしれませんね。
例えば、がん抑制遺伝子のBRCA1とBRCA2が原因遺伝子である「遺伝性乳がん・卵巣がん症候群」では、BRCA1変異を持つ人は、70歳までに7割くらいが乳がん、5割くらいが卵巣がんを発症します。BRCA2変異は割合が少し低く、70歳までに6割くらいが乳がん、1割くらいが卵巣がんを発症します。このように、遺伝子診断で変異を持っていることがわかったからといって、決して100%がんになるわけではないのです。ただし、リスクが高いということは確定します。
一部、「フォン・ヒッペル・リンドウ病」などのように、浸透率100%という腫瘍もあります。この遺伝性腫瘍は、VHLというがん抑制遺伝子の1つに変異があることで、目や腎臓など、いろいろなところに腫瘍が出ます。VHL遺伝子に変異を持っていると、ほぼ100%がんになりますが、これはまれなタイプで、多くの遺伝性腫瘍は浸透率100%ではありません。原因となる変異を持っていても、生涯がんにならない人もいます。
実際に診療している中で、先生はどのような患者さんに対して「遺伝性のがん」を考えるのですか?
「同じ血縁者の中に同じがんが何人もいる」「若くしてがんになる」「両側ある臓器の両側ががんになる」といった場合に、遺伝性のがんを考えます。あとは、例えば右側の乳房に3個がんができたとか、大腸に3年ごとに3か所がんができたとか、ひとりで複数がんができたといった場合にも考えます。それから、乳がんの数年後に卵巣がんができたなど、臓器は違っても、1つの遺伝子に関連した複数のがんが同じ患者さんにできる、というような場合にも、遺伝性のがんを考えます。
子どものがんは、全てが遺伝性のがんと考えて良いでしょうか?
子どものがんは白血病が最も多く、中枢神経のがん、肉腫、甲状腺がんなどもあります。大勢のがんの子どもの遺伝子を調べた研究がいくつかあるのですが、いずれも、生殖細胞系列に変異があった、つまり、遺伝性のがんだったのは、8%前後という結果でした。つまり、約9割の子どものがんは、遺伝ではないと言えるのです。
人間は、受精卵というたった1つの細胞から、10か月後に生まれるまでに何十兆個という数まで細胞を増やします。その過程は「発生」と呼ばれ、とてもたくさんの遺伝子の複製と細胞のコピーが繰り返されます。
発生の過程では、大人では通常使われなくなっているような、細胞増殖に関わるさまざまな遺伝子が、たくさん使われるタイミングがあります。そのため、どうしても偶発的な遺伝子変異が起きやすいとされており、それが子どものがんの原因のほとんどだと考えられています。つまり、子どものがんは、受精から誕生までに起きた出来事が原因になるものが多いと考えられるのです。

遺伝性のがんに関して、先生にはどのような問い合わせが多く寄せられますか?
当院ががんセンターで、私が遺伝性のがんの専門外来を担当している関係もあると思うんですが、ご自身が乳がんや大腸がんにかかっていて、治療中もしくは治療が落ち着いており、お子さんがいるという患者さんからの問い合わせが多数あります。その中でも一番多いのは、「自分のがんが子どもに遺伝するのか?」という質問ですね。「もし子どもに遺伝しているとしたら、それはどのくらいの頻度なのか?」「どういう対策ができるのか?」という質問が、圧倒的に多いです。ご自身もがんの治療で大変だと思うのですが、「自分よりも、子どものことがとにかく心配」という方がほとんどですね。「自分よりも」というのはネガティブな意味ではなく、「自分のがん治療はすでに大きな流れが決まっていて、このまま受けていれば大きな間違いはない」という感触が、今の治療で得られているという印象です。
子どもが心配という理由のひとつに、遺伝性疾患、特に遺伝性腫瘍の遺伝子診断が、日本ではほとんど保険で認められていないということがあると思います。海外では、遺伝性の乳がんなのかを調べる遺伝子検査は保険でカバーされており、若いうちから気軽に受ける人が多くいます。ところが日本では、「検査を受けたいが、どこで受けられるのかわからない」「保険が使えない場合、一体いくらかかるのだろうか」など、公表されていることが少ないという点も、不安の原因になっています。遺伝子検査は、子どもの診断に関わってくるので、子どもが心配というお問い合わせにつながっています。
自分が遺伝性腫瘍の変異を有しているかどうかは、誰でも病院へ行けば調べてもらえますか?
採血のみで調べられるので、技術的には誰でも検査は可能です。しかし、家系で最初に検査をする人は、「典型的な遺伝性のがんを発症している人」が最も適していると言えます。先程、常染色体優性遺伝で伝わるがん関連遺伝子の変異を持っていた場合、この変異が子どもに受け継がれる確率は50%とお伝えしました。これは、お子さんが2人いる場合、確率的には1人は変異を受け継いでいない可能性があると言えます。ですから、片方のお子さんが遺伝子検査をして、その人に変異がないという結果が出たとしても、「この家系は遺伝性腫瘍の変異を持っていない」と言い切ることはできないのです。このように結論が出せない検査を避けるためにも、できるだけ、遺伝性腫瘍に特徴的ながんを発症している患者さんを最初に検査することが重要です。誰でも検査することはできますが、誤診を避けるためにも、最初にその家系の誰を調べるのかがとても重要になります。遺伝子検査をお勧めできる人とお勧めできない人がいるということを、知っておいていただければと思います。
また、遺伝子検査は、どこの医療機関でも行われている検査ではありません。日本で遺伝性腫瘍の診療を行っている病院は、まだ限られているので、もし検査を希望される場合には、事前に病院に問い合わせるようにしましょう。
遺伝性腫瘍の診療を行っている病院は、どうやって見つけたら良いのでしょうか?
遺伝性腫瘍を診療する専門医の資格はいくつかあるのですが、その中に、「臨床遺伝専門医」という、小児の遺伝病や神経難病などを全て含めた遺伝性疾患全般に対する専門の資格があります。臨床遺伝専門医を持っている医師と医療機関のリストは、「日本人類遺伝学会」のホームページに掲載されていて、誰でも見ることができます。このリストは、専門医の中でも非常に経験豊富な医師には「指導医」のところにマークがついており、遺伝性腫瘍の診療を受け付けている医師/医療機関には、「腫瘍」のところにマークがついています。これを参考に、指導医がいて、遺伝性腫瘍の診療を受け付けている病院をリストから探すのが、簡単な見つけ方のひとつです。都道府県別に全国のリストがありますので、お住まいの都道府県で調べていただけば良いと思います。当院は、私が指導医で、他に2名、腫瘍を専門としている臨床遺伝専門医がいます。
病院で受けるがんの遺伝子検査は、保険適用なのでしょうか?
遺伝性のがんは長い間、保険で受けられる検査がなかったのですが、数年前から保険収載されはじめ、現在では「網膜芽細胞腫(RB1遺伝子)」「甲状腺髄様がん(RET遺伝子)」「遺伝性乳がん卵巣がん症候群:HBOC(BRCA1/2遺伝子)」が保険適用されています。このうち、RB1とRETは、遺伝性疾患の診断として認められていますが、BRCA1/2は、現時点ではPARP阻害薬という抗がん剤がその人に効果的かどうかを調べる目的(コンパニオン診断)のみで、生殖細胞系列変異を調べることが、保険でできるようになっています。つまり、BRCA1/2の遺伝子検査は、がんを発症した人しか保険適用されないので、お子さんの遺伝子診断を受けたい場合は自費になります。
保険適用ではない遺伝子検査は、自費診療になります。以前は「研究に参加していただく」という形で、患者さんに無料で遺伝子検査を行っている大学などがいくつもありました。ところが2年前に医療法が改正され、「研究機関で行った検査は、診療に供してはいけない」という法律に変わり、検査の精度管理を行わないと患者さんに結果を返せなくなりました。採算の取れにくい遺伝性疾患の検査は、これまで現場の医師の熱意に支えられてきた側面があるため、この新しい法律とどう折り合いをつけるかというところが、大きな課題のひとつだと考えています。
遺伝を心配している方が自費で検査を受けざるを得ない状況については国も問題視しており、年々、状況は変わってきています。今後、遺伝子検査の保険適用は徐々に広まっていくでしょう。また、保険適用されているBRCA1/2の遺伝子検査は、2020年4月から抗がん剤の選択に限らず、遺伝性乳がんの診断としても実施できるように適応が拡大される予定です。まだがん患者さんしか保険では検査ができませんが、家系で誰か1人の診断がつけば、間接的ではありますが、その情報を使って血縁者の診断が進むようになるわけで、これは非常に大きな1歩だと思っています。

インターネットで購入できる市販の遺伝子検査にも、がんのリスクを調べる検査がありますが、遺伝性腫瘍の変異も調べられますか?
インターネットで販売されている多くの遺伝子検査は、いわゆる多因子疾患としての、がんのリスクを検査結果という形でご本人に返しているもので、遺伝性のがんに関連する遺伝子は抜いて検査しているものがほとんどです。遺伝性のがんに関することは、医療機関で相談するようにしてください。
自分ががんのリスクが高い遺伝的体質だと知った場合、自身でできる「がんの予防につながる行動」は何かありますか?
まず、「遺伝性腫瘍の原因となる遺伝子変異を持っているとわかった場合」を例にお話します。遺伝性乳がん卵巣がん症候群を起こすBRCA1/2変異では、NCCNガイドラインという国際的ながんの診療ガイドラインがあり、「何歳で何の検査を受ければよいか」ということが書かれています。具体的には、「18歳から自分で触診をしましょう」「25歳から医療機関で検査を受けましょう」などです。
こうした変異を持っていた場合、検査もより詳しいものを受けることになります。通常の乳がん検診では、若い人は超音波検査、ある程度の年齢になるとマンモグラフィーというケースが多いのですが、BRCA1/2変異を持つ場合は、造影MRIという、通常の検診ではあまり行われない、非常に早期のがんを見つけられる精度が高い検診が勧められています。この検診も、2020年4月から保険診療として実施できる予定です。
このように、遺伝性腫瘍の原因となる変異を持つとわかった場合には、自分で日常的にチェックする、定期的に専門の検査装置がある医療施設の紹介を受けて受診するなど、かかっている医療機関から、ガイドラインに基づいたアドバイスや紹介を受け、行動することになります。
次に、多因子疾患としてのがん全般について、お話します。欧米人と日本人に共通して最もがんのリスクを上げるとわかっているのが「たばこ」です。ですから、禁煙をするのが自分でできる最も効果的ながん予防と言えます。
2位は、欧米人と日本人で異なります。欧米人の場合は肥満や食生活ですが、日本人の場合、食事はそんなに大きな要素にならないようです。太り過ぎもやせ過ぎも良くないですが、食事に対しそこまで神経質になる必要はないでしょう。
一方、日本人の2位は「感染症」です。例えばHPVによる子宮頸がん、肝炎ウイルスによる肝がん、そしてヘリコバクターピロリによる胃がんなどが3大巨塔です。日本では、子宮頸がんワクチンの副作用に関して揉めていますが、予防接種に関しては他の国に比べて非常に遅れています。そのため、感染症がコントールできず、感染症によるがんが2位になっているのです。がん予防という観点からは、予防可能なものは、積極的に予防していくことが大事だと考えます。
難しい「がんと遺伝」の話を、横井先生は、一つひとつ、ゆっくりと穏やかな口調で、わかりやすく説明してくださいました。
お話を伺い、がん家系は、医学的には血縁者を対象に調べるものであり、「遺伝性のがんの原因となる変異を持っていても、必ず全員ががんを発症するわけではない」ということがわかりました。また、日本人のがんのリスクを上げる環境的要因の2位が感染症だということには、大変驚きました。がん予防における禁煙の重要性を再認識するとともに、日本のがん予防対策についての課題を、しっかりと理解することができました。(遺伝性疾患プラス編集部)