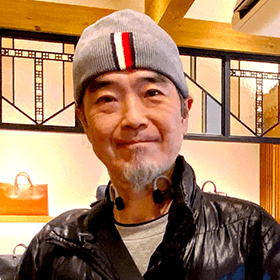体内の臓器や組織に異常なタンパク質凝集体「アミロイド」が沈着することで発症する、トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー(TTR-FAP)。アミロイドが沈着する場所によって、さまざまな症状が現れます。例えば、筋力低下、声のかすれ、などの末梢神経障害、排尿障害、消化器症状などの自律神経障害です。その他、貧血、体重減少といった全身症状も生じます。なお、常染色体優性(顕性)という遺伝形式をとる遺伝性疾患で、「全身性アミロイドーシス」に含まれる形で国の指定難病対象疾病になっています。
今回お話を伺った森内さんは、TTR-FAPのお母さん・妹さんを亡くされた経験をお持ちで、ご自身もまたTTR-FAPと診断を受けています。症状の進行に伴い、約30年続けていた小学校教諭の仕事から離れることを決意。吹奏楽の指揮者としても活躍していましたが、同じく、続けることが困難となりました。また、プライベートでは、ご自身のお子さんへTTR-FAPのお話をすることを強く悩まれた経験もお持ちです。生体肝移植の手術と入院治療を受けられ、現在はお住まいを北海道から福岡に移住して通院治療を受けています。「病気をきっかけに周りの人のあたたかさを知り、感謝することができた」という森内さん。これまでのご経験、そして、「シロクマセンセイ」名としても広く病気の発信を行う活動についても、詳しくお話を伺いました。
TTR-FAPの症状で「怠けている」と誤解も。葛藤を抱えながら診断へ
2014年頃に、妹さんの主治医からTTR-FAPの可能性とともに検査を勧められたと伺いました。当時、どのような症状が現れていましたか?
今振り返ると、TTR-FAPによる症状は2014年以前から現れていました。しかし、妹の主治医から自身の病気の可能性について説明を受けるまでは自覚していませんでした。例えば、吹奏楽の指揮が一曲終わり、ステージから降りた途端に、ものすごく喉が渇くんです。それは、2リットルほど水を飲んでも全く渇きが収まらないほどです。今思えば、少しずつ体重も落ちていたと思います。一方で、「指揮者はハードワークだから、皆さんも同じような状況なのかな」と考えていました。今思うと、これはTTR-FAPの症状だったんですね。アミロイドが唾液腺に沈着すると唾液が出にくくなることがあり「口の渇き」などの症状が現れます。妹の主治医から「お兄さんも、検査を受けられてはいかがでしょうか?」と説明を受けた後からは、それまでは自覚もしていなかったさまざまな症状を感じるようになっていきました。
症状がつらいと感じる一方で、検査を受けることをなかなか決断できませんでした。自分の中に「もし自分がTTR-FAPだったら、嫌だ。怖い」という気持ちがあったからです。頭では「早く検査を受けたほうが良い」と理解しているのですが、心の中の「怖い」という気持ちが上回っていたのです。このような不安な状況なので、インターネットを中心にTTR-FAPに関わる情報を検索して調べました。そして、さまざまな情報を目にするたびに、さらに不安でいっぱいになる日々を送っていたのです。そこから受診して検査を受ける決断をできたのは、それから約2年後の2016年頃のことです。
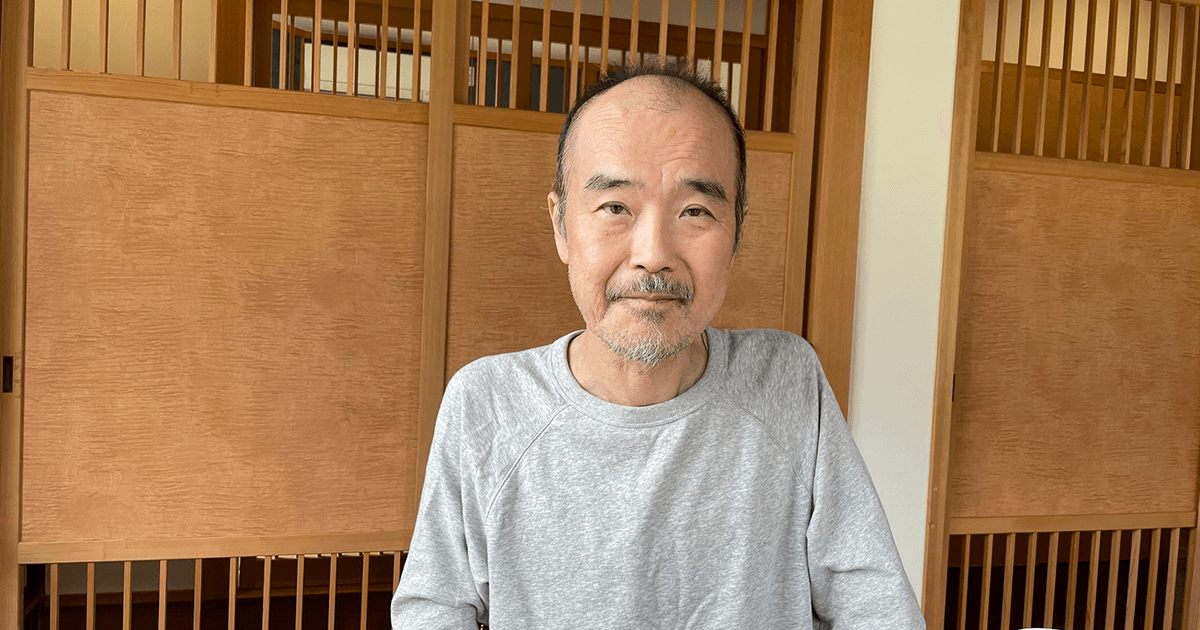
検査を受ける決断をできたのは、どのような理由からですか?
症状の進行に伴い、小学校教諭の業務にも影響が現れてきたことが理由の一つです。僕はもともと身長180cm、体重100kg近くある体格で、割と陽気な性格でした。だから子どもたちが喜んで僕にしがみついてきて、いつも子どもたちをぶら下げて歩いているような小学校教諭だったんですね。このことが「シロクマセンセイ」という名前の由来にもなっています。しかし、ある健康上の取り組みの一環として口呼吸を控えるようになり(編集部注:当時限定の取り組みで、現在はやめておられます)、「今まで笑ってた森内先生が、全く笑わなくなった」と子どもたちは受け取ったようでした。次第に、子どもたちと距離が生まれていきました。子どもたちと遊ぶ体力を使わなくて良くなった一方、僕はとても悲しかったです。
加えて、体の衰えにより周囲からは「怠けている」と誤解されることが増えました。例えば、起立性低血圧により、しゃがんで立つ動作では必ずめまいが生じていたんです。具体的な業務でいうと、子どもたちの作品を教室の壁に貼る作業によって立ちくらみがひどくなり、作業に長時間かかるようになりました。このような変化によって、「今までの森内先生は積極的に働いていたのに、最近、怠けているようだ」と誤解されているのではと感じるようになりました。このような背景から「このままではいけない」と次第に考えるようになりました。妹の主治医が検査を受けることを勧めてくれなければ、僕はずっと決断できなかったと思います。妹の主治医がせっかく心配して声をかけてくれたことだし、「何もしないと先生に悪いから」という思いで受診することを決意しました。
当時お住まいだった北海道から、熊本の病院へ受診が必要だったと伺いました。長距離の移動は負担になりませんでしたか?
自分の場合は「必要なことだから」という認識が強かったので、大きくは気にならなかったです。受診することを決めたら、受診日に病院へ行くために飛行機のチケットを取らないといけないですよね。そして飛行機のチケットを取ると「飛行機に乗らないとお金がもったいない」と思うようになります。このように、あとは受診するのみ、という状況に自分を持っていきました。
確定診断を受けた時、どのようなお気持ちでしたか?
当日は、それほど大きなショックを受けませんでした。そこから徐々に症状を自覚するようになって、「自分はショックを受けていたんだな」と実感していったという状況です。おそらく、当時、自分の中で“安全弁”のようなものが働いていたのだろうと思います。自分で、自分の感情を押さえつけていたというか…。もし押さえつけなかったら、すぐに感情があふれてしまうような状態だったのかもしれません。その後、入院治療を受けた際に、自分の気持ちと嫌でも向き合わなければいけなくなるのですが。この時は、そこまで自分の気持ちとは向き合えない状況でした。
絶望の中でも前を向けたのは、「子どもたちとの約束を果たす」という決意
どういったお気持ちで、小学校教諭の仕事を離れる決断をされましたか?
繰り返しになりますが、症状の進行に伴い業務に対応できなくなっていったため、やむを得ず決断しました。僕は当時、特別支援学級の2年生の担任でしたが、マラソン大会の練習の時に、症状の進行を痛感したんです。なぜかというと、1年前は6年生と一緒に全速力で走れていたくらいだったのに、2年生の子たちとも同じように走れなくなっていたからです。いくら走っても追い付けなくて、最後には低学年の子どもたちが走る距離を完走できなくなりました。その他にも、校庭で子どもが遊具から落ちたと情報があり、急いで向かわなくてはいけないときがあったんです。ダッシュして急いで向かおうと思った矢先に転び、自分で起き上がれなくなったんですね。目の前でけがをしているかもしれない子どもを助けに向かえない自分に絶望しました。
こういった経験を積み重ねていき、「もう無理だ」と痛感しました。周りの先生方や子どもたちに迷惑をかけたくないというのが、小学校教諭の仕事から離れると決意した理由の一つです。吹奏楽の指揮者としての活動にもやりがいを持っていましたので、病気を理由にさまざまなことをあきらめなくてはならない現実に深く悲しみを覚えました。ただ、この時は「また小学校教諭に戻れる」と信じて疑っていませんでした。手術を受けることで、症状が改善されて全て元通りになると思っていたんです。しかし、現実の体は決して元通りとは言えない状態でした。
手術治療を受けた後は、どのようなお気持ちでリハビリを受けていましたか?
体が元通りにならないことに絶望し、それでも、「必ず、子どもたちのもとへ戻る」という思いで必死にリハビリを受け続けました。しかし少し治ったと思ったらそれ以上に悪化するような日々を過ごしました。来る日も来る日も「全然前に進んでいない」と思う中で、僕は少しずつ心を病んでいきました。「こんな苦しいのに全然良くならない。もういい」と思い、自らの命を絶つ選択を選ぼうと考えたこともあります。それでも、選択を誤らなかったのは、手術を受ける前に子どもたちに「必ず戻ってくるからね」と約束したからです。「子どもたちに嘘をつくなんて、教師失格だよ」と、自分に言い聞かせたのです。
子どもたちとの約束があったからこそ、頑張れたのだと思います。後に復職し、その後も続けている発信活動は、子どもたちに感謝の気持ちを伝えるために、恩返しの気持ちも込めて行っているという側面もあります。
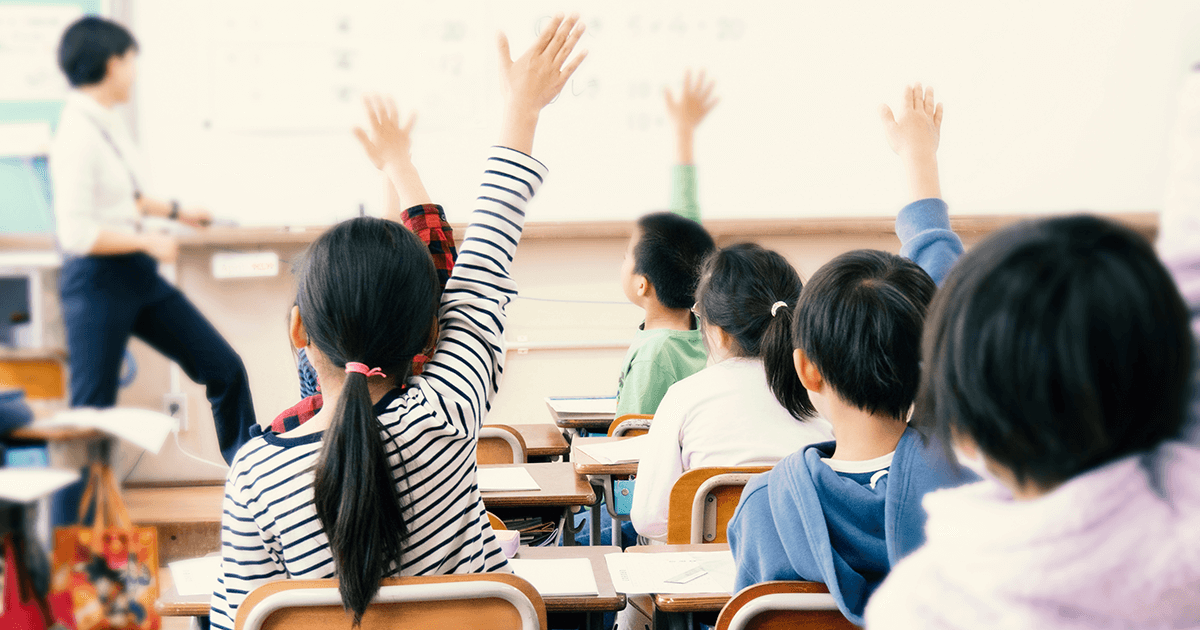
子どもたちへの恩返し、「病気の経験を伝える」教師に
現在の発信の活動を通じて、お子さんたちからはどのような反応はありますか?
10年以上前の教え子から、SNSを通じて連絡をいただくときはうれしいですね。子どもたちが小学校を卒業して、中学・高校と成長していく過程で僕のことを知らない友だちができますよね。そういう子たちが「シロクマセンセイってどんな人?」と聞くと、教え子たちが「本当に良い先生なんだよ」と言ってくれるんです。こんな風に教えてもらえることが本当にうれしくて。自分は、本当に子どもたちに生かされているんだなと考えさせられます。
教師として復職して、学校はいかがでしたか?
復職してから学校を離れるまでの最後の半年間は、いただいた恩を返すために働きました。偶然ですけどその時の6年生は、ちょうど僕が本格的に闘病を始めた頃に担当していた子どもたちの学年でした。僕が病気になったことを知って、お手紙を一人ずつ書いてくれたこともありました。だから、復帰した僕が、特に「ありがとう」を伝えたかった学年であり、6年生で卒業を控えた学年でもあったんです。大変ありがたいことに、6年生の小学校最後の授業を僕が担当することになりました。道徳の授業として、担任の先生が僕に指導を任せてくれた時間だったんです。その時間を使って、「あなたたちのおかげで、先生はこの場所に戻ってくることができました」と感謝をお伝えし、病気のお話もさせていただきました。子どもたちは、みんなボロボロ泣いていて、真剣に話を聞いてくれていたように感じます。後日、保護者の方々のお話をうかがっていると、少し問題も抱えるような子の親御さんも「先生の授業を受けて、子どもの様子が良い方に変わったようです」と喜んでくださいました。この時の経験が、今の発信活動につながっています。
TTR-FAPをはじめとした遺伝性疾患の当事者として、社会へどのような発信をしていきたいですか?
病気のことを含めて、「このことを伝えるために、僕は教師になったんだ」と考えています。自分の命が尽きるまで、この発信を続けたいと思います。
TTR-FAPを我が子へ説明し後悔も、今は「伝えて良かった」
お子さんへご自身の病気を伝えることを迷っていたと伺いました。それでも娘さんへ伝えることを決断された経緯について、教えていただけますか?
同じTTR-FAPの妹が亡くなった時に、決断しました。少しずつ、僕の体も自由がきかなくなってきたことも影響していました。TTR-FAPは原因となる遺伝子が子どもへ引き継がれる可能性がある病気だと、我が子へ伝えなければならないと思いました。しかし、我が子がどのように受け止めるのか不安で、なかなか決断できずにいました。決めてもなお、とても気が重かったです。でも、言わざるを得ないということで伝える日を迎えました。
僕は妹の葬儀に臨んだ後、北海道に戻りました。その途中、娘の居る場所へ立ち寄りました。病の発症を伝えるためです。しかし、なかなか話を切り出せなかったんです。「またね、バイバイ」と言うときまで話すことができず、娘の家の駐車場に車を停めて、ようやく話し出せたほどでした。僕は運転席、娘は助手席に座っていたため、娘の表情はよく見えない状態で伝えました。話しながらふと横を向くと、娘が鼻を真っ赤にして、目を腫らして、静かに泣いているんです。その光景を目の当たりにしたときは、「やはり、話すべきでなかったのではないか」と思い、激しく後悔しました。今振り返っても、つらかったです。それでも今は「伝えて良かった」と心から思っています。

当時の僕は、自分のことだけでいっぱいでした。「もし我が子に恨まれたら、どうしよう」と、自分が悪者になるのが嫌だったのだと思います。今改めて考えると、この病気が遺伝する可能性も含めて、あのとき伝えて本当に良かったと思います。
「あなたは悪くない」病気を理由に望みを諦めないで
最後に、遺伝性疾患プラスの読者にメッセージをお願いいたします。
一番お伝えしたいのは、「負けないで欲しい」ということです。遺伝性疾患というだけで、きっと誤った偏見にさらされた経験のある方もいらっしゃることでしょう。僕も、これまでそういった場面を見てきました。そういった目にさらされる可能性を理由に「周囲に病気を明らかにできない」という方もたくさんいらっしゃいます。もし明らかにしない選択をされた方がいらっしゃったら、それでも「決してあなたは悪くない」とお伝えしたいですね。あなたが悪いのではなく、受け入れない社会側に問題があると考えるからです。皆さんそれぞれ違っていて当然だと、僕は考えます。僕が病気を公表し、発信しているのはそういう意味も込めているからです。
それともう一つ、もし叶えたい夢や希望があるのであれば、ご自身の病気を理由に諦める必要はありません。どうやったらご自身やご家族が幸せになれるか、ぜひ考えてみてください。
現在は、ご自身の病気に関わる経験を伝える活動を行う森内さん。このために「教師になったんだ」と力強くお話されている姿が印象的でした。また、お子さんへTTR-FAPの原因遺伝子が引き継がれる可能性があることを伝えるにあたり、深く悩まれた経験もお話してくださいました。「もし我が子に恨まれたら…」と後悔した時間があったものの、現在は「伝えて本当に良かった」とのことです。
遺伝性疾患の当事者・ご家族の皆さんが、今後もし苦しい現実と向き合わなければならない時がきたら、ぜひ「もし叶えたい夢や希望があるのであれば、ご自身の病気を理由に諦める必要はありません」という森内さんのメッセージを思い出していただきたいと思います。(遺伝性疾患プラス編集部)