sanakiさんは、お子さんが生後10か月の頃に、シュワッハマン・ダイアモンド症候群と診断を受けました。最初はミルクアレルギーの疑いから大学病院へ転院。育児日記・写真の症状記録で医師とコミュニケーションを取るなど工夫を重ねていきました。その後、シュワッハマン・ダイアモンド症候群の特徴の一つである脂肪便(脂肪が多く悪臭のある便)をきっかけに膵臓の機能不全の可能性にたどりつき、最終的にシュワッハマン・ダイアモンド症候群と判明。2024年のインタビューの際には、お子さんの就園のハードルの高さ、同じ疾患を持つ方とつながることの難しさなど、希少疾患を取り巻く課題について話してくださいました。その後、ご自身で遺伝性疾患プラスのシュワッハマン・ダイアモンド症候群解説記事に掲載されている医療施設に連絡したり、同じシュワッハマン・ダイアモンド症候群のご家族とつながって交流したりなど、さまざまな変化があったとのこと。新たにつながった先生経由で、海外の患者団体ともつながることができたそうです。前回、「シュワッハマン・ダイアモンド症候群の当事者・ご家族から、日々の楽しい話も聞いてみたい」とおっしゃっていたsanakiさん。約1年経った今、ご自身の行動により、どのような変化があったのか詳しく教えていただきました。
思い切って医療施設へ連絡、先生へ「当事者家族とつながることの難しさ」を相談
シュワッハマン・ダイアモンド症候群解説記事に掲載の医療機関へ、どのように連絡を進めましたか?
解説記事に記載されている2施設について、まず、ウェブサイトの情報を確認しました。そこには、シュワッハマン・ダイアモンド症候群の研究情報が紹介されており、問い合わせ先も明記してありました。そこで、思い切ってメールでご連絡をしたところ、現在も研究を続けておられる先生をご紹介いただくことができました。先生とは、主にメールでコミュニケーションを取っています。

また、以前から悩んでいた、同じシュワッハマン・ダイアモンド症候群の当事者家族とつながることの難しさについて相談しました。すると、先生から「できる限り、協力したい」と前向きなお言葉をいただきました。実際に先生方とつながることができただけでも本当にうれしかったですし、親身に相談に乗っていただけたことが非常に心強かったです。
その他、先生からのご紹介で、米国のシュワッハマン・ダイアモンド症候群の当事者支援団体「Shwachman-Diamond Syndrome Alliance」とつながることができました。現在、日本には当事者団体がない状況だと思いますので、とてもうれしかったです。また、米国の当事者支援団体の創設者の先生ともつながることができました。
日本と米国の先生方と一緒に、日本時間の2025年4月26日(土)に当事者の方・ご家族の方向けのオンライン交流会を開催します。詳細は、コチラのページからご確認ください。

先生からの紹介でつながった米国の支援団体、知りたい情報もわかった
米国の当事者支援団体を紹介してもらい、どのような気持ちでしたか?
海外でもシュワッハマン・ダイアモンド症候群の研究が進められていること、同じ状況で生活している方々がいることを知り、うれしく思いました。
一方で、最初は「英語のウェブサイトの内容を理解できるかな?」など不安でいっぱいでした。私は、決して英語が得意なタイプではないからです。しかし、翻訳ツールやアプリを使うことでほとんどストレスを感じずに内容を把握できることがわかり、ほっとしました。便利なツールがある時代で、本当に良かったと思います。
海外の患者団体とつながることで、新しく得られた情報や気づきはありますか?
海外の患者団体のウェブサイトには、当事者ご家族の体験談ページがあります。そこには、私が今最も知りたいと思っているシュワッハマン・ダイアモンド症候群の当事者の「日常生活の様子」や「成長の過程」の情報がつまっています。これらの情報を知ることができたのは、非常に大きな収穫でした。特に、我が子と同年代のお子さんや症状が似ている方々の体験談は、繰り返し読んでいます。
遺伝性疾患プラスの記事掲載をきっかけに国内のご家族ともつながる
遺伝性疾患プラスでの記事掲載後、同じシュワッハマン・ダイアモンド症候群の日本人ご家族とつながることができたそうですね?
そうなのです。大変驚きました!同時に、非常にうれしく、ありがたく、心強く感じました。こんなに早く、複数名からご連絡をいただけるとは思っていなかったからです。私だけでなく、同じように情報を求めている方々がたくさんいらっしゃるのだと実感しました。一方で、個人で情報発信を続けるには限界があります。例えば、私個人で発信したものが、インターネットで「シュワッハマン・ダイアモンド症候群」と検索したときに必ずしも上位に表示されるとは限りません。ですから、遺伝性疾患プラスを通じて発信できて良かったです。
現在は、主にSNSのダイレクトメッセージなどで皆さんとコミュニケーションを取っています。少しずつではありますが、同じ疾患と向き合うご家族とのつながりが広がってきました。先生方にサポートしていただきながら、今後は、オンラインで家族同士の交流の場をつくっていきたいと考えています。

就学の話などを共有、以前より将来への心構えができるように
同じ疾患のご家族とつながったことで、気持ちはどのように変化しましたか?
以前は「これから、我が子にどのようなことが起きるのだろう。どのように対応していけばいいのだろう…」など、“わからないことばかり”という現実に不安な気持ちが強くありました。しかし、我が子より年上のお子さんの成長過程や日常生活について教えていただけるようになり、不安は減りました。「〇〇の場面ではこうやって対応すれば良さそう」「〇〇は、我が家でも同じような状況になるかもしれない」といった具体的なイメージが持てるようになったからです。また、「〇年後、もし同じような悩みが生じたときには□□さんに相談してみよう」と、将来に対する心構えもできるようになってきました。
特に「知ることができて良かった」と感じているのは、我が子より年上のお子さんたちの就学や就労の経験です。もちろん、将来の予測は難しいです。本人の成長状況や体調によって、状況が変わってくるからです。それでも、皆さんのお話から「就学前の準備」「学校生活の様子」「具体的な相談先」などを知ることができ、以前よりも今後の見通しを立てやすくなったと感じています。
前回お伺いしたときに、もし同じ疾患の当事者・ご家族とつながることができたら、「日々の楽しい話も聞いてみたい」とお話されていましたが、実現しましたか?
もちろん苦労しているお話も出ますが、楽しく過ごしているお子さんの様子や成長の喜びなども共有しています。こういったお話を聞くことで、「我が家も、日々を楽しみながら過ごしていきたい」という気持ちが強くなりました。また、以前よりも「こんな風に〇〇すると楽しめるかもしれない」と前向きに考える時間が増えたように思います。
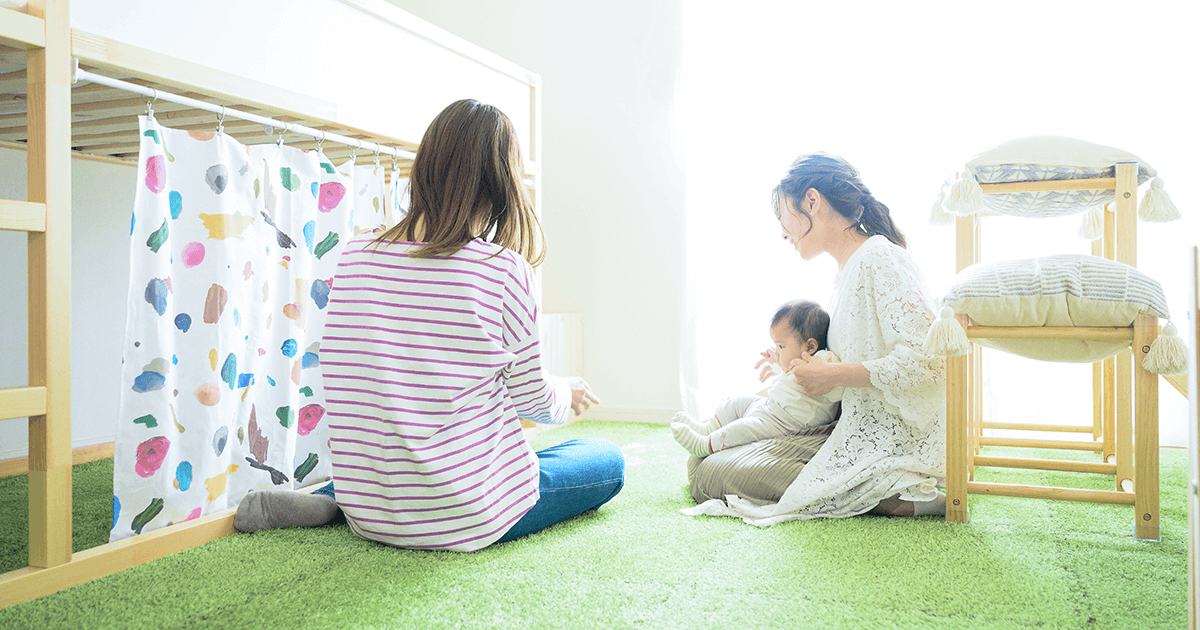
メディアやSNSの活用など、ご自身にあった方法でつながってみて
同じ疾患の当事者やご家族とつながることができずに悩んでいる方々へ、メッセージをお願いします。
希少疾患の場合は、特に、同じ疾患の方々とつながることが難しいと実感しています。同時に、私を含め、当事者ご家族は日常生活を送りながら情報を求め続けているのだと思います。メディアやSNSの力を活用できる現代だからこそ、つながることができる可能性が広がっているのではないでしょうか。私の場合は、遺伝性疾患プラスでの記事掲載がきっかけでした。何がきっかけになるかはわかりませんので、ぜひ、皆さんにあった方法を探してみていただければうれしいです。
最後に、シュワッハマン・ダイアモンド症候群の情報は、今もなお決して多いとは言えない状況です。ご家族と話していると、「もっと、〇〇の情報も知りたい」という声があがっています。今後の研究の進展や、関連情報が増えていくことを期待しています。
希少疾患「シュワッハマン・ダイアモンド症候群」と向き合うご家族とつながり、楽しく過ごしているお子さんの様子などを伝え合っているというsanakiさん。「以前よりも、前向きに考える時間が増えたように思います」と心持ちの変化を教えてくださいました。前回、今回とお話をうかがってきた中で、研究者の先生方や国内外のご家族との「つながり」が、不安でいっぱいだったお気持ちの変化に大切だったように感じました。
日本には患者団体がないような希少疾患の場合、同じ疾患のご家族とつながることは決して簡単なことではありません。そういった状況の中でも、医療施設へ連絡をしてみる、海外の患者団体とつながってみる、などさまざまな行動を自ら起こしているsanakiさんのお話が印象的でした。もし、同じように「つながることが難しい」と悩んでいるご家族がいらっしゃったら、sanakiさんのお話を思い出していただけるとうれしいです。(遺伝性疾患プラス編集部)







