体の形や位置を保つために細胞同士をつなぐ「結合組織」。この結合組織が弱くなる結合組織疾患では、全身にさまざまな症状が出現します。遺伝性結合組織疾患には、マルファン症候群、ロイス・ディーツ症候群、家族性大動脈瘤などがあり、それぞれ原因となる遺伝子が異なります。中でも家族性胸部大動脈瘤・解離では、心血管系の症状以外はほとんど現れません。そのため、診断において遺伝学的検査(遺伝子検査)を受けることが重要とされています。
今回お話を伺ったのは、家族性胸部大動脈瘤・解離の当事者のご家族・鈴木さん(仮名)です。ご家族の方が34歳の時に、大動脈解離を発症。医師から結合組織疾患の説明を受けましたが、当時は遺伝学的検査を受けない選択をし、正しい病名がわかりませんでした。ご本人が「もし重い病気だったら、自分には知らせないでほしい」という考えを持っていたためです。しかし、鈴木さんはご自身で情報を集める中で、確定診断を受けることの大切さを痛感。遺伝性疾患プラスの記事を一緒に確認するなどしつつ、遺伝学的検査に関わるコミュニケーションをご本人と続けていきました。結果、ご家族の方は遺伝学的検査を受け、大動脈解離の発症から約4年の月日を経て、確定診断を受けることができたといいます。正しく診断を受けたほうが良いと考える一方で、「遺伝性疾患かどうかを、はっきりさせることに不安も感じていた」という鈴木さん。今回は、診断に至るまでのご家族・医療施設とのやり取りを中心にお話を伺いました。
検査を拒否するご家族、話に耳を傾けてもらえず
最初、どのような症状をきっかけに病気を疑われていたのでしょうか?
家族が大動脈解離を発症して、手術を受けたことがきっかけです。当時、手術を担当した医師から「結合組織疾患の可能性があります」と説明を受けました。当時、本人は34歳だったため、若年での発症を踏まえて結合組織疾患の説明を受けたという経緯です。しかし、本人の希望で遺伝学的検査は受けず、具体的な病名はわかりませんでした。

ここから本人が検査を受けることを決意するまで、約4年の時間がかかりました。本人が、「もし重い病気だったら、自分には知らせないでほしい」という考えを持っていたためです。このような背景から、大動脈解離を発症した当時は、私から本人へ検査を受けることを積極的に勧めませんでした。
ご家族へ検査を勧められるようになったきっかけについて、教えてください。
インターネットで情報収集する中で、「疾患を確定させたほうが良いのではないか」と考えたためです。その頃、大動脈解離を発症してから約半年経っており、本人は相変わらず検査を受けることをかたくなに拒否していました。きっと、本人は「重い病気で治療法がない場合、知るのが怖いから」と考えていたのだと思います。最悪のケースを想像すればするほど、病名を知ることが怖かったのだろうと思います。そのため、私の話にもなかなか耳を傾けてもらえませんでした。
医師に対しては、「患者本人は、重い病気の場合、診断名を知らされたくないという考えです」とお伝えてしていました。そういったことも影響していたのか、先生方は配慮してくださり、病気に関する情報は伏せてくださっているような様子でした。今思えば、「私にだけ、病気のことを詳しく教えてほしい」と、もっとお願いすれば良かったと感じています。こうして、家族の検査に対する考え方が変わらない日々が続きました。
正しく診断を受けることの大切さ、記事の中の医師の言葉が伝わる
遺伝性疾患プラス記事をきっかけに、ご家族とのコミュニケーションが変わってきたと伺いました。詳しく教えていただけますか?
きっかけは、遺伝性疾患プラスのLINEで届いた「小坂仁先生が回答!遺伝子治療Q&Aコーナー」という記事でした。希少疾患の場合、患者さんはいるものの、なかなか確定診断がつかない方々がいることを知りました。例えば、米国で承認された遺伝子治療の臨床試験を日本で行うことになった際に、患者さんが見つからず、診断をつけるところから始めないといけない段階だったそうです。特に遺伝性疾患の場合は、希少疾患で患者さんの数が少ない状況にも関わらず、日本ではあえて隠すようなところがある、というお話もあり、腑に落ちました。家族にもこの記事を一緒に見てもらい、「なぜ正しく診断を受けることが大切か」について、改めて一緒に考えました。また、記事には治験の解説もあったことも大きかったです。仮に、今は対症療法しか受けられない状況でも、正しく診断を受けることで、今後、治験参加の可能性があることを家族に知ってほしかったのです。
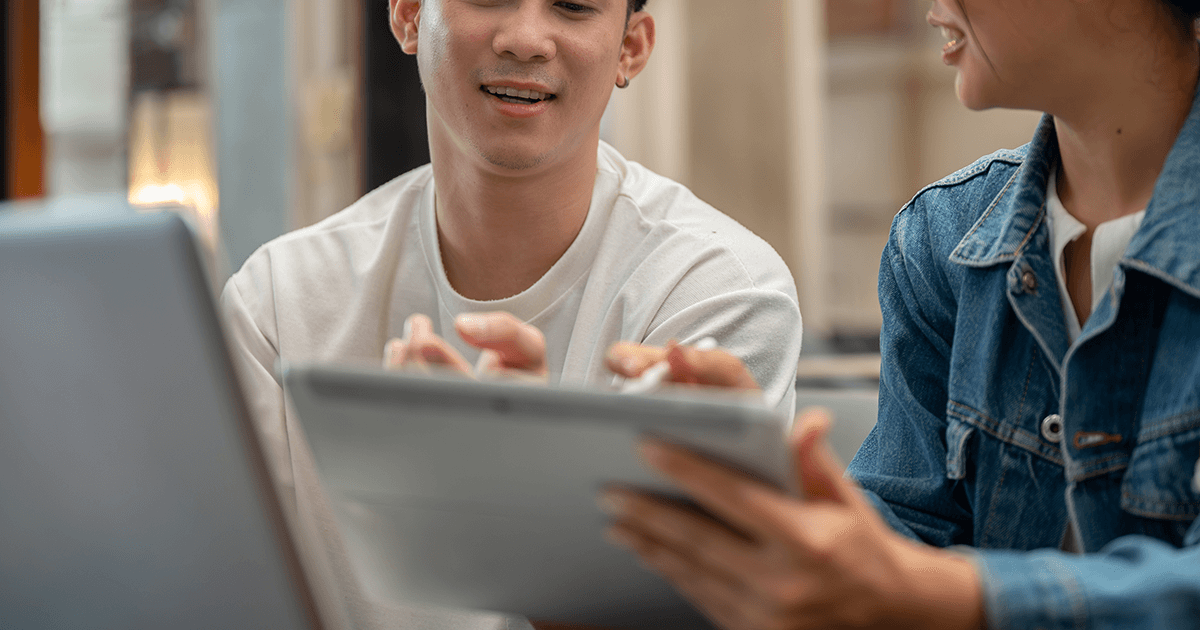
これまでも、幾度となく私から本人へ遺伝学的検査を勧めてきたので、「もし今回も断られたら、今後、説得はやめよう」と決めていました。そのため、緊張しながら、「今回も、やっぱりだめかな…」と不安に思いながら本人と向き合いました。すると、本人も私の話に耳を傾けてくれたようで、記事を一緒に読みながら、少しずつ心変わりしていくようでした。きっと、専門家であり、かつ、第三者である先生方の客観的なご意見という点も、本人が話を聞いてくれた要因の一つだったと思います。
その後、どのようにして遺伝学的検査を受けることになったのでしょうか?
まずは、「遺伝カウンセリングを一緒に受けてみよう」と話しました。遺伝カウンセリングで専門家のお話を聞いたうえで、あくまでも検査を受けるかどうかの最終的判断は本人にお任せするというスタンスです。もともと、私は「遺伝カウンセリング」という制度を知りませんでしたが、「NPO法人日本マルファン協会」のウェブサイトで紹介されていたことをきっかけに知りました。大動脈解離の情報を調べる中でマルファン症候群の患者団体のウェブサイトにたどりつき、本当に良かったです。
結果的に、遺伝カウンセリングの場で、本人が「遺伝学的検査を受ける」と決意しました。「治療において、遺伝学的検査をすることは特別なことではないです」と説明を受けたことで、本人の心が動いたように感じました。そのまま検査を受け、約2か月後に結果をもとに診断を受けたという経緯です。大動脈解離を発症してから約4年後、本人が38歳の時でした。

病名が明らかになることへの不安も…でも、診断を受けてホッとした
確定診断を恐れる当事者と向き合う側も、苦しい思いをされていたのではないかと想像しています。
そうですね。正しく診断を受けたほうが良いと思う一方で、「遺伝性疾患であることをはっきりさせることで、家族が社会的に不利益を被るかもしれない」と感じることもありました。具体的な話があったわけではないですが、医師の話からもそういったことを感じる場面があったからです。そのため、家族へ遺伝学的検査を勧め続けることに自信を持てずにいました。これから先ずっと病気と向き合い続ける本人の気持ちも考慮すると、素人である自分には責任が大きいと感じていました。遺伝学的検査を受けるか判断するために必要な情報が、全てそろっている自信もなかったからです。加えて、病名が明らかになることで家族の精神状態に悪い影響を与えるかもしれないと考えると、私自身、不安で仕方ありませんでした。
受診していた病院には、がんの当事者向けの相談窓口がありました。がんに限らず、遺伝性疾患についても、もっと気軽に相談できる場所が病院で開かれていると良いのかなと思います。
ようやく確定診断を受けた時、どのようなお気持ちでしたか?
少し、明るい気持ちになりました。家族の体が弱いことに変わりはありませんが、病名が明らかになり、ホッとしたのは事実です。これまで、「もし、思っていた以上に重い病気だったら、本人に対して申し訳ない」という不安を抱えていたので。一方で、家族が対象となる治験は現在行われていないと知り、残念に思いました。今後の研究開発に期待したいと思います。
確定診断を受けたことで、医師に具体的な相談ができるように
確定診断を受けたことで、日常生活にはどのような変化がありましたか?
大動脈瘤が新たにできていないかを確認するため、本人は定期的に検査を受けています。その他、日常的に血圧をコントロールする薬を飲んでいます。また腎臓の障害も起きていることから、定期的に採尿・採血をして状態を見ています。確定診断を受けたことで、薬について医師と具体的に相談できるようになったのは良かったと感じています。
最後に、遺伝性疾患プラスの読者にメッセージをお願いいたします。
希少疾患は、他の疾患と比べて情報を探すことがとても大切だと実感しています。決して情報が多くない分、苦労されることがあると思います。そして、当事者はもちろん、ご家族もきっと大変なことが多いでしょう。そのような中でも、楽しいことを見つけながら、ご自身をいたわっていただければと思います。
正しく診断を受ける大切さを考える一方、遺伝性疾患だと確定することに不安も感じていたという鈴木さん遺伝学的検査を拒否していたご家族に対して、検査を勧め続けることが良いのか自信がなかったことなど、ご自身の葛藤も教えてくださいました。その中でも、遺伝性疾患プラスの記事などをもとに正しく診断を受ける大切さを具体的に説明され、遺伝カウンセリングを一緒に受ける提案へつなげていました。必要な情報をお伝えしたうえで、あくまでも決定権は当事者であるご家族へゆだねていたコミュニケーションも、印象的です。もし、同じように当事者へのコミュニケーションで悩まれているご家族がいらっしゃったら、一つの選択肢として鈴木さんの経験を知っていただければと思います。(遺伝性疾患プラス編集部)
関連リンク







